多田銀銅山
採鉱技術を伝える廃鉱山を蘇らせる |

自由に入坑できる近世の「青木間歩」 |
| 大規模ショッピングセンターで賑わう猪名川パークタウンからさほど遠くないところに、「銀山地区」という静かな集落がある。かつてはその名のとおり銀を採る鉱山で栄えた町だった。現在も山腹の至る所に採鉱の跡が洞穴として残っている。本稿では、天正期・寛文期・元禄期の3度に渡って隆盛を見た多田銀銅山について、採鉱に係る技術を中心にレポートする。 |
|
|
|
|
|
田銀銅山は、川西市・猪名川町・池田市など7市町に分布し、黄銅鉱・斑銅鉱・方鉛鉱・輝銀鉱などを産する鉱山である。伝承によれば、これを開いたのは源
満仲(延喜12(912)~長徳3(997)年)らしい。藤原家に仕えて摂津国・越後国・陸奥国などの国司を歴任した後、摂津国多田庄に土着して「清和源氏」の祖となった人物である。天禄元(970)年、銀鉱石を発見した者を武士に取立て白金山奉行に任じたという。
多田銀山は、天正年間(1573~1593年)には豊臣 秀吉の所領となる。海外に目が開いていた秀吉は、明から白 水善を招聘して「南蛮吹1)」という優れた精錬技術を導入した。
|
 |
 |
|
図1 豊臣政権の財政を支えたという「台所間歩」(左)と秀吉が千成瓢箪の幟を挙げることを許したという「瓢箪間歩」(右)の現状 |
多田銀山は目覚ましい発展を遂げ、ここから上納される銀は大坂城の金蔵を満たし政権の財源を賄ったと伝えられる。しかし、慶長3(1598)年、死期の近づいた秀吉は、突然、多田銀山の閉鎖(「銀山払い」)を命じた。この理由は謎であるが、秀頼が豊臣家を再興させる時の資金にするため秘匿したとの伝承がある。
吉の後に天下を制した徳川 家康は、多田銀山を重視せず天領とはしなかった。ところが、家綱が第4代将軍であった万治3(1660)年に、極上の銀を産する鉱脈が発見された。ただちに幕府はここを天領にし、銀山奉行はじめ65名の役人に支配(寛文元(1661)年)させた。翌年には役所の諸施設が整い吹屋(精錬業)が呼び集められて「銀山町」が成立したようだ。
|
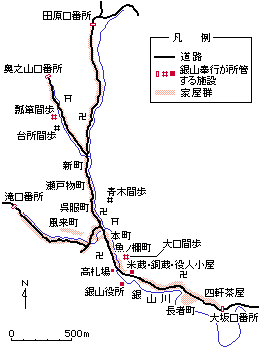 |
|
図2 江戸時代の銀山町 |
町は柵で囲われ4か所の出入口には番所が築かれた。採鉱夫もたくさん集められた。ここに住む者は外に出ることを制限された反面、銀山町においては「諸事停止(ちょうじ)たるものなし」として農民に禁止されている娯楽も許されたし衣食住の自由も認められたから、彼らの生活を支えるさまざまなサービス業も銀山町に集まった。
町の戸数は「銀山三千軒」と称され、人口は1~1.5万人ほどであったと推定される。鉱山で成功した富裕者の住む「長者町」、風来者が多い「風来町」、魚市が立った「魚ノ棚町」、呉服屋や瀬戸物屋が集まった「呉服町」と「瀬戸物町」、茶屋が軒を並べた「四軒茶屋」などの地名が往時の繁華を髣髴とさせる。相撲や芝居の興行もあった。
鉱を行う労働者は「外財」(げざい)と総称されたが、その作業は鉱石を掘り出す「掘子」4名と鉱石を外に運び出す「手子」4名が1組になって行われ、これを「槌壱挺前」と呼んだ。昼夜8交代で作業が行われ、各組は昼夜1回ずつ間歩に入ったので1日の労働時間は6時間であった。掘子の具体的な作業は、「鉄鋏箸」で鏨(たがね)を挟んで岩に当てこれを鉄槌で打って岩を砕いていくこと。
|
 |
|
図3 「青木間歩」に残る手掘りの坑道(年代不詳) |
切羽は縦3尺5寸(約105cm)、横2尺(約60cm)で、これに縦に1筋、横に3筋の切込みを入れて8等分し、それぞれを順に切っていく。岩質が軟らかい場合は1日に2尺ほども進んだようだが硬い場合は1寸がやっとだったという。掘削の技術は徒弟関係を通じて伝承され、一定の技量を認められた者には認証が与えられた。この認証は全国どこの鉱山でも通用したという。
そのほかにも、坑内には、坑道の表面が崩れないように支保工を施す「山留大工」、測量や地層傾斜の測定に基づいて掘削の方向を指示する「振矩(ふりがね)師」などもいた。いずれも技術の要る仕事であったのに加えて、絶えず危険にさらされていたし、“よろけ”という病に罹って若死にするケースも多く、そのために彼らの賃金は極めて高かったという。
柵内にあったたくさんの間歩のうち「大口間歩」と「瓢箪間歩」は「直山」(じきやま)とされた。これは、坑道などの整備費用を幕府が負担する代わりに採れた鉱石の一定割合を幕府に運上させるというもの。運上された鉱石は入札により吹屋に払い下げられた。
多田銀山の生産量は、天領になった直後の寛文4(1664)年に年間の出銀高1,500貫目(約5.6t)、出銅高75万5,800斤余(約453.5t)を記録したのが最大で、その後は減少に転ずる。その理由は坑内の湧水だ。瓢箪間歩では、6年の末になってようやく水抜普請が完成し、地下120~150mのところに秀吉が隠し置いたとされる大鉱脈も発見したものの、昼夜兼行で水抜き作業を続けても排水できず、奉行は新たな水抜普請の許可を江戸に願い上げたがこれは余りに膨大な費用のために却下された。そのため採取できる資源が乏しくなってきたのだ。このような状況であったところにさらに打撃を与えたのが延宝4(1676)年の大洪水であった。2つの間歩に川の水が大量に流れ込み約100人が犠牲となる大惨事が生じた。翌年から始めた水抜普請も成功せず、瓢箪間歩の浅いところだけを採掘するしかなくなった。これを機に直山制度は廃され、すべての間歩が民間が自費で採鉱して(有望な間歩では資金の前貸しの仕組みはあった)
|
 |
|
図4 「鼓銅図録3)」に描かれた寸法樋による揚水の様子 |
幕府に運上金を納める「請山(うけやま)」となった。
こで、当時の鉱業のネックとなった湧水処理技術を見ておこう。湧水が少量の場合は桶で揚水されたが、坑道が深くなって湧水量が増えると図4のような「寸法(すぽん)樋」と呼ぶ手動式揚水ポンプが用いられた。これは、1辺12cm程度の四角形をした長さ3m程度の木製の筒に弁のついた木製のピストンを差し込んだもの。これを何挺も上下に並べてリレー式に揚水した。
の生産が低迷する中、元禄年間(1688~1710)に銅の生産量が増えた。元禄7年には36万斤余の出銅を記録し、多田銀山は銅山として再び活気を見せ始める。この時代、全国的に銅の産出が多く、3年に別子銅山が発見されたほか尾去沢銅山や阿仁銅山を始めかつて金銀山として名を馳せた山々が銅山として復活している。
銅はわが国の最大の輸出品になった。幕府は、輸出用の銅を確保するため全国の銅山に出銅量を割り付け、これを大坂2)に集めて買い上げ(14年に「銅座」を開設)、銅吹屋に賃吹きさせた後、長崎に廻送してオランダと中国に売ることとした。従って、銅鉱は、鉱山の近くで粗銅(あらどう)にまで加工され、大坂で南蛮吹を施して精銅にすることになるが、多田については南蛮吹がすでに行われていたので精銅の形で大坂に送られた。
銅は、最大で産出量の9割が輸出に回されていたが、鉱山の疲弊と国内で貨幣鋳造の需要が増えたため次第に輸出は振るわなくなった。享保6(1721)年には幕府が銅を買上げる制度が廃されて、民間の売買に幕府が運上金を課す方式に変更された。多田銅山においても、正徳5(文化5(1808)年には出銅高80斤余まで低下している。
明治維新の後、政府は「開坑規則」(明治2(1869)年)、「鉱山心得」(3年)、「鉱山其他諸坑業の規則」(6年)などを発して法制の整備を図った。また、外国の技術の積極的な移入により鉱山経営の近代化への道が開かれたが、それには大きな資金が必要であった。銀山町で稼行したのは島根の鉱業家
堀 伴成であった。彼は近代的な製錬所を建設して事業の拡大を図った一方、地元の者に請負わせた採鉱作業では、掘削・運搬・排水について近世と比べて
|
 |
|
図5 堀精錬所の遺構、未調査のため個々の遺構の用途は明らかになっていないが排煙を背後の山の頂上まで導くなど当時としては配慮された設備であった |
|
 |
|
図6 鑿岩機で掘られた「青木間歩」(表題の写真も)の内部、平成12(2000)年に整備され入坑が可能になった |
たいした技術的進歩は見られない。
鉱作業が近代化されるのは大正時代のようだ。近代鉱物史の中に埋没してしまっている多田鉱山での状況は詳らかにしないが、鉱山懇話会「日本鉱業発達史」(ロゴス出版)によれば全国的にはこの頃から鑿岩機や火薬の使用が進んだという。
まず、鑿岩機については、明治20年頃から圧縮空気による鑿岩機が輸入され始めたが、大正6(1917)年頃から国産の優良な電気鑿岩機が製造されるようになり、これまで手掘坑夫の養成に苦労していた各鉱山において目覚ましく普及した。鑿岩機の導入により硬質部の採鉱が容易になったのに加え、坑道が1.8~2mほどに拡張され、坑内の運搬の効率化にも寄与した。併せて、支保工に用いる木材にクレオソートなどの防腐剤を使用して耐久性の向上が図られた。
次に、火薬の使用については、陸海軍の火薬製造所で生産されたダイナマイトが明治15年頃から別子銅山において使用されたとされるが、大正6年に民間のダイナマイト製造が許可されて使用が拡大した。
また、排水設備についても、明治13年に蒸気機関を動力とする排水機が佐渡鉱山に導入されているが、42年に電気タービンポンプが国産化されて使用が広まった。従来の寸法樋はおおむね1基の揚程1.1m、揚水量0.15m3/分であったのに対しタービンポンプは揚程150~170m、揚水量2.8m3/分であったから、水替人夫2,500人以上の仕事を1台のポンプで行う計算になる。
このような近代化の結果、採鉱の効率は大いに向上し、鉱夫1人あたりの鉱産額は明治40年で530円だったのが10年後の大正6年には1,670円に、20年後の昭和2(1927)年には2,020円に増大した。こうして全国で鉱業が活気づいたから、銅は再び輸出品として重要な地位を占める。銅の価格は国際的な景況に支配されることとなり、生産量の増減は景況に応じて大きく振幅した。
第2次世界大戦の影が濃くなると、銅は軍需品として重視されるようになり、積極的に増産するよう推奨された。この機に応じて「日本鉱業」は19年に多田の鉱業権を手に入れたが、生産に着手する前に終戦を迎え同社の開発は戦後に持ち越された。ボーリング調査を29年に行い、その結果から地下180mまで竪坑を到達させたのが昭和40年。翌年から生産を開始した。月産粗鉱量1,000tを目指し竪坑を地下270m付近まで伸ばしたが、そのあたりで鉱脈は切れており、鉱量の枯渇により47年に生産を停止した。
|
 |
|
図7 銅銀山に関する資料を展示する「多田銀銅山悠久の館」 |
同社は、多田銀銅山の80%はすでに掘り尽されていたと分析している。こうして多田銀銅山の1,000年に渡る歴史に幕が下りた。
れらの遺跡について、猪名川町は平成12(2000)年度から調査を開始し、19年に銀山町の歴史を紹介する「多田銀銅山悠久の館」をオープンした。古絵図・古文書・鉱山道具などを展示している。敷地の裏からは江戸時代の代官所の跡、正面には堀 精錬所の跡が望め、往時の賑わいを偲ぶことができる。また、町の調査をもとに、国の文化審議会文化財分科会は、多田銀銅山が「江戸から明治に至るまでの鉱山のあり方や産業技術史を考える上で重要」とその価値を認め(27年6月)、国の史跡に指定された。
「悠久の館」をはじめ鉱山のあったあたりは、猪名川町や電鉄会社が紹介するハイキングコースになっており、多くの人が訪れている。自由に入坑できる青木間歩も近代の採鉱技術を体感するのに役立つ。
(参考文献) 猪名川町史編集専門委員会「猪名川町史 第2巻」及び「同 第3巻」
1)先ず、精錬において「吹く」とは、金属を取り出すために鞴(ふいご)で強い風を送って高い火力で鉱石を溶かすことを指す。南蛮吹は、銀が鉛に吸収されやすい性質を利用して銀と銅を分離する高度な技法で、①まず銀と銅が混在する金属に鉛を溶かして「合銅(あわせどう)」という合金を作り、②この合金を加熱し、銅と鉛の融点の差を利用して精銅と含銀鉛に分離し、③含銀鉛に通気・加熱し、鉛を酸化鉛にして灰に吸収させる「灰吹法」という方法により銀を回収する、というもの。その名が示すようにヨーロッパで中世から知られていた技術を移入していると考えられるが、日本の南蛮吹は使用する鉛を少なくして、合銅から鉛を流出させるときに強く圧迫する(この工程を「鍰(しぼ)る」と呼ぶ)など、独特の工夫を加えたものになっている(浅尾
直弘「住友の歴史 上巻」(思文閣出版)による)。なお、別説では、文亀永正年間(1501~1520年)に銅屋
新左衛門が山下村(現在の川西市山下町付近)に製錬所を設け「山下吹」という技法を用いて黄銅鉱から銅を抽出したと伝えられるのが、南蛮吹と同じ技術ではなかったかとしている。
2) 南蛮吹を開発した蘇我 理右衛門の長男が住友家に入って大坂で銅吹屋を開業(元和9
(1623)年)するに当たって、契約を結んだ同業者にこの技法を教えて協業体制を作ったので、結果的に優良な銅を大量に精錬できるのは大坂だけとなり、大坂に流通が集中することになったのである。
3) 住友家が銅の採掘から精錬までの過程を紹介するため文化初年ころに制作刊行した鉱山学の書。増田 綱 撰、丹羽 桃渓 画。
|
|