140年間 敦賀港を見守り続けた灯台
|

立石岬の突端から敦賀湾の船に灯火を送る「立石岬灯台」 |
| 灯台は、日常生活で目にする機会は少ないが、船舶の航行を支援することにより海上交通の安全と効率化に寄与し、海洋国家であるわが国の社会経済活動を支えている重要な施設である。今回は、140年にわたって灯火信号を送り続けている敦賀市の立石岬灯台を訪れた。 |
|
が国の開国は嘉永7((1854)年の「日米和親条約」に始まる。下田(静岡県)などを開港するが、沿岸に岩礁が多い上に航路標識が備わっていなかったので、航行する外国船に恐れられていた。各国の強い要求に基づき、慶応2(1866)年に英・米・仏・蘭と結んだ「改税約書」において「日本政府ハ外國交易ノ為メ開キタル各港最寄船々ノ出入安全ノタメ燈明臺、浮木、瀬印木等ヲ備フベシ」と規定し、野島埼(千葉県)、観音埼(神奈川県)、剣崎(神奈川県)、神子元島(静岡県)、潮岬(和歌山県)、樫野埼(和歌山県)、伊王島(長崎県)、佐多岬(鹿児島県)の 8灯台を建設することとした。また、翌年にイギリスと結んだ「大坂約定」においても友ヶ島(和歌山県)、江埼(兵庫県)、和田岬(兵庫県)、六連島(山口県)、部埼(福岡県)の5灯台の整備を取り決めた(以上の13灯台を「条約灯台」と呼ぶ)。
日本人で西洋式灯台を知る者はなかったので、幕府はフランスとイギリスに技術指導を依頼していた。大政奉還により幕府の業務を引継いだ明治政府によりこの仕事は続けられ、明治2(1869)年にわが国で最初の西洋式灯台として観音埼灯台が完成した。設計などは慶応元(1865)年に来日していたフランス人技師ヴェルニー(Franc,ois Le'once Verny、1837〜1908年)が指導した。その後、明治元年に来日したイギリス人のブラントン(Richard Henry Brunton、1841〜1901年)により、神子元島灯台や樫野埼灯台をはじめ多くの灯台が建設された。ブラントンが9年に帰国した後は、彼の「灯台築造方首員」の任務はマクリッチ(James MacRitchie、1847〜1895年)に引き継がれた。一方、この頃から日本人
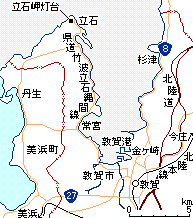 |
| 図1 敦賀港と立石岬灯台の位置 |
が灯台の設計・施工・灯火管理などの技術を習得し、灯台関係の外国人技術者は次第に解雇されていく。マクリッチの解雇は12年12月。「灯明番教授方」として管理要員の養成を担当していたチャルソン(Gorge Smith Charleson、1844〜1916年)が最後に離任したのは14年5月であった。
稿で紹介する「立石岬灯台」は敦賀湾の北端にある。初点灯は明治14年7月。この灯台は前記の条約灯台ではなく、わが国の独自の判断で建設に至ったものだ。外国船だけでなく、自国の船舶の航行にも灯台が有用であることを認識したのだ。
この時期にこの地に灯台が建設されたのは、わが国の鉄道建設の歴史と大いに関係がある。維新直後の明治2年、政府は東西両京を結ぶ鉄道を建設することを決定し、これと最も近い日本海側の港湾である敦賀に着目して、琵琶湖から野坂山地を越えて敦賀に達する路線も優先的に建設することを決定していた。この路線は相当の難工事が予想されたため、経路の比較選定に時間を費やし、着工は13年4月であった。立石岬灯台も、同じ時期に敦賀港の活用のために計画されたと考えられる。
立石岬灯台の建設までの経緯は参考文献に詳しい。それによると、この灯台の現地調査が行われたのは11年6月のことだった。マクリッチはじめ灯台局の職員が上陸して、敦賀港に船舶を誘導する上でこの位置が最適であることを確認したとある。また、この時点で灯台と「退息所」という職員宿舎の設計ができていたこと、使用するレンズの規格も決まっていたことが示されている。だが、灯台の建設はすぐには着手されなかった。この理由として、マクリッチが、"当地は商業が盛んであり、民間または地方政府による灯台建設の動きがあるから、灯台局の費用の節減のためこれを許可するのが望ましい"として建設を延期するよう進言していたことが挙げられる。
これが、13年4月になって、急遽、国により建設工事が開始されたのは、先に述べたように、鉄道建設の具体化があった。当時、鉄道局と灯台局はともに工部省に属していたから、このような連携は当然のことである。鉄道の開通により敦賀は東京や神戸と結ばれ、敦賀港は横浜港・神戸港・関門港とともに国営港に選定され、日本海側で唯一の第1種重要港湾になった。
 |
図2 現地の説明板に掲載されているかつての立石岬
灯台(撮影時期不明) |
35年に敦賀とロシアのウラジオストックを結ぶ国際航路が開かれ、ウラジオストックからシベリア鉄道を利用すれば最短距離でヨーロッパにつながることになる。敦賀はヨーロッパへの玄関口として華やかな発展を見た。そして、この航路の安全を確保したのが立石岬灯台だったのだ。敦賀市の市章にこの灯台がデザインされていることからも、敦賀におけるその重要性が理解できる。
参考資料からの引用を続けると、建設当時、灯台の保守や運用のために、職員2名、水夫・小使各1名、傭船1艘であったという。立石は、敦賀と陸続きとは言え、行商人が年に数人しか来ない僻地であり、生活物資は船で調達するしかなく、灯台守の日常生活の維持は労苦の多いものだった。また、宿舎は1棟だったので、職員2家族の共同生活も環境としては劣悪だった。
灯火は、当初は石油ランプであったが、大正3(1914)年にアセチレンガス灯、昭和13(1938)年に電灯と、光源が近代化されていった。
 |
図3 灯台に使用されている花
崗岩は当地で採取されたと記
録されている |
そして、35年に灯器を交換して1)運用が自動化され、翌年に職員の配置が解除されて灯台は無人となった。
賀市のコミュニティバスに乗っておよそ40分。海岸線に沿って走る県道竹波立石縄間線を行くと、終点の立石に着く。そこからさらに200mほど歩いて灯台に向かう登山道を登ると、まぶしいほどに真白に塗装された灯台が姿を現す。灯台が建つのは標高114mのところで、そこに灯火までの高さ7.9mの灯台が建つ。現地の案内板によると、15.0万カンデラの単閃白光が10秒ごとに発せられ、20.5海里(約38km)先まで達するそうだ。
小ぶりな灯台であるが、その形は均整がとれて美しい。灯台の下半分を構成する「附属舎」は花崗岩でできており、
入口の上部に日本語と英語で初点灯日が記されている。灯台の西には退息所があったが、今では除却されて礎石と井戸の跡だけが残っている。前庭の日時計は当初のものと思われる。
立石岬灯台の建設が始まったときにはマクリッチはすでに離任していた。本灯台は、日本人への技術移転が完了し、外国人の指導を脱して日本の技術者が独立して灯台を建設できるようになった節目を画す記念すべき作品だ。それが140年を経て未だ現役で活躍していることの感慨が、この灯台をいっそう美しく見せる。
 |
 |
図6 退息所に附帯していた
井戸の跡 |
図7 日時計は当初の
ものと考えられる |
 |
 |
| 図4 灯台の天頂にある風向計 |
図5 日本語と英語で初点灯日を記す銘板 |
|
(2021.09.18)
(参考文献) 灯台研究生「−明治の灯台の話(2)−立石埼灯台」(燈光会「燈光」平成16年12月号所収)
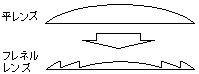 1) 撤去した第4等フレネルレンズは敦賀市立博物館へ寄贈された。フレネルレンズとは、1822年にフランスの物理学者・土木技術者であるフレネル(Augustin
Jean Fresnel、1788〜1827年)が考案したもので、レンズの厚みを薄くするために断面をのこぎり状にした。灯台用レンズは巨大であるため、通常の設計では原材料費が高いこと、重量が重いこと、製造に手間がかかることからこのレンズを考案したという。 1) 撤去した第4等フレネルレンズは敦賀市立博物館へ寄贈された。フレネルレンズとは、1822年にフランスの物理学者・土木技術者であるフレネル(Augustin
Jean Fresnel、1788〜1827年)が考案したもので、レンズの厚みを薄くするために断面をのこぎり状にした。灯台用レンズは巨大であるため、通常の設計では原材料費が高いこと、重量が重いこと、製造に手間がかかることからこのレンズを考案したという。
|
|